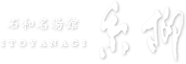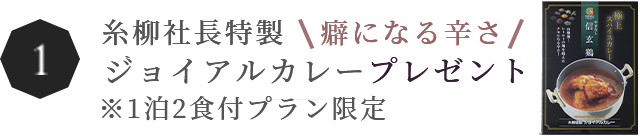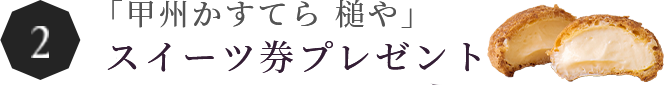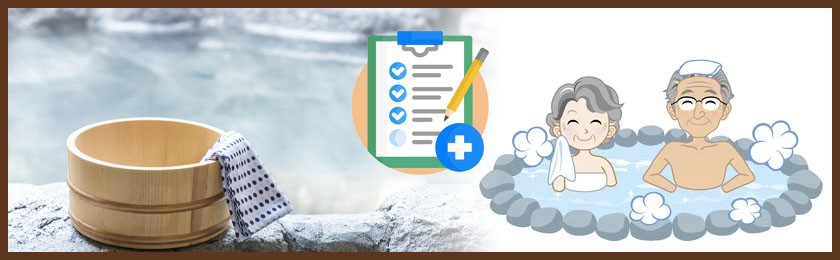2023.02.17糸柳便り
温泉・療養泉の定義|人工温泉や鉱泉との違いも解説
「温泉」という言葉を知らない人はいないと思いますが、「温泉の定義」までしっかりと把握している方は、意外と少ないのではないでしょうか。温泉の定義は、「温泉法」で明確に定められており、温度の条件や成分の条件を満たす必要があります。
当記事では、温泉や療養泉の定義について詳しく紹介します。これから温泉旅行に行こうとしている方や、温泉のことについてもっと詳しく知りたいと思っている方は、ぜひ参考にしてください。
1.温泉の定義
「温泉」と一口に言っても、その定義は「温泉法」によって以下のように明確に定められています。
温泉は、昭和23年に制定された「温泉法」により、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、表1の温度又は物質を有するものと定義されています。
引用:環境省「温泉の定義」
【表1】
1. 温度(温泉源から採取されるときの温度) 摂氏25度以上 2. 物質(以下に掲げるもののうち、いずれか一つ)
- 溶存物質(ガス性のものを除く。):総量1,000mg以上
- 遊離炭酸(CO2)(遊離二酸化炭素):250mg以上
- リチウムイオン(Li+):1mg以上
- ストロンチウムイオン(Sr2+):10mg以上
- バリウムイオン(Ba2+):5mg以上
- フェロ又はフェリイオン(Fe2+,Fe3+)(総鉄イオン):10mg以上
- 第一マンガンイオン(Mn2+)(マンガン(Ⅱ)イオン):10mg以上
- 水素イオン(H+):1mg以上
- 臭素イオン(Br-)(臭化物イオン):5mg以上
- 沃素イオン(I-)(ヨウ化物イオン):1mg以上
- ふっ素イオン(F-)(フッ化物イオン):2mg以上
- ヒドロひ酸イオン(HASO42-)(ヒ酸水素イオン):1.3mg以上
- メタ亜ひ酸(HASO2):1mg以上
- 総硫黄(S)[HS-+S2O32-+H2Sに対応するもの]:1mg以上
- メタほう酸(HBO2):5mg以上
- メタけい酸(H2SiO3):50mg以上
- 重炭酸そうだ(NaHCO3)(炭酸水素ナトリウム):340mg以上
- ラドン(Rn):20(百億分の1キュリー単位)以上
- ラジウム塩(Raとして):1億分の1mg以上
※含有量(1kg中)
引用:環境省「温泉の定義」
日本は世界でも有数の温泉国であり、多くの人から愛されています。温泉は、上記のように様々な成分が含まれているので、公共の浴用や飲用に使用する場合は、都道府県知事などの許可を得なければなりません。
利用許可を申請する際には、温泉の成分に関する分析書を併せて提出する必要があり、「鉱泉分析法指針」で定められています。
1-1.25度未満の温泉はある?
温泉法の定義によれば、「温度」か「物質」の条件を満たせば「温泉」と呼びます。そのため定義上、25度未満の温泉は存在すると言えます。ただし、成分が含まれているからといって、海水や泥水、入浴剤を入れたお湯など、全ての水が「温泉」となるわけではありません。あくまで、【地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)】と定義されているので、地中から湧き出ているものが対象です。
また、液体ではなく「水蒸気」「ガス」であっても、条件を満たしていれば「温泉」と呼ぶことも分かります。
2.療養泉の定義
温泉と似た言葉に「療養泉」というものがあります。療養泉は温泉法ではなく、環境省の「鉱泉分析法指針」で以下のように定義されています。
療養泉とは、温泉(水蒸気その他のガスを除く。)のうち、特に治療の目的に供しうるもので、表2の温度又は物質を有するものと定義されています。
引用:環境省「温泉の定義」
【表2】
1. 温度(源泉から採取されるときの温度) 摂氏25度以上 2. 物質(以下に掲げるもののうち、いずれか一つ)
- 溶存物質(ガス性のものを除く。):総量1000mg以上
- 遊離二酸化炭素(CO2):1000mg以上
- 総鉄イオン(Fe2++Fe3+):20mg以上
- 水素イオン(H+):1mg以上
- よう化物イオン(I-):10mg以上
- 総硫黄(S)〔HS-+S2O32-+H2Sに対応するもの〕:2mg以上
- ラドン(Rn):30(百億分の1キュリー単位)=111Bq以上(8.25マッヘ単位以上)
※含有量(1kg中)
引用:環境省「温泉の定義」
温泉の中でも「療養」に貢献する温泉を「療養泉」と呼びます。療養泉には、以下のような泉質が必ず名づけられ、それぞれに適応症があります。
- 単純温泉
- 二酸化炭素泉
- 炭酸水素塩泉
- 塩化物泉
- 硫酸塩泉
- 含鉄泉
- 硫黄泉
- 酸性泉
- 放射能泉
- 含よう素泉
3.温泉と人工温泉の違い
温泉について調べていると「天然温泉」と「人工温泉」という言葉を聞いたことがある方も多いでしょう。一般的に天然温泉は、いわゆる温泉法に基づく「温泉」を指します。
一方で人工温泉は、地中から湧出したものではなく、お湯に温泉成分を添加させたものです。具体的には、鉱石や天然鉱物由来の薬剤が使用されており、厚生労働省からの承認を得ている医薬品もしくは、医薬部外品に該当する必要があります。そのため、お湯に入浴剤を入れただけでは「人工温泉」とは呼べず、温泉法に規定されている泉質や適応症・禁忌症などを掲示することもできません。
メジャーな人工温泉としては、トロン温泉やトゴール温泉、光明石温泉などが挙げられます。
4.温泉と鉱泉の違い
温泉と似た用語に「鉱泉」という言葉があります。温泉と鉱泉の違いを簡単に述べると、温泉は気体も含む、鉱泉は気体を含まず液体のみ、という区分です。
温泉と鉱泉の定義 温泉(※1) 地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。) 鉱泉(※2) 鉱泉とは、地中から湧出する温水および鉱水の泉水で、多量の固形物質、またはガス状物質、もしくは特殊な物質を含むか、あるいは泉温が、源泉周囲の年平均気温より常に著しく高いものをいう。
※1引用:環境省「温泉の定義」
上記の通り、温泉には「地中より湧出する水蒸気およびその他のガス」を含みますが、鉱泉には含まれないことが分かります。なお、鉱泉の温度条件・含有物質に関する定義は、基本的に温泉と同じです。
5.【泉質別】日本で代表的な温泉地
最後に、日本で代表的な温泉地を泉質別に紹介します。温泉や療養泉の定義を知ったことで、また違った角度から温泉を楽しめるでしょう。気になった温泉地には、ぜひ足を運んでみてください。
| 泉質 | 有名な温泉地の例 |
|---|---|
| 単純温泉 |
|
| 二酸化炭素泉 |
|
| 炭酸水素塩泉 |
|
| 塩化物泉 |
|
| 硫酸塩泉 |
|
| 含鉄泉 |
|
| 硫黄泉 |
|
| 酸性泉 |
|
| 放射能泉 |
|
| 含よう素泉 |
|
また、山梨県の石和温泉は、ぶどう畑の中に湧き出した温泉(青空温泉)として知られ、山梨県屈指の人気の温泉です。アルカリ性単純泉の温泉が、心地よく皆様の体の疲れを癒します。
まとめ
温泉の定義は、地中から湧き出した温水、鉱水及び水蒸気その他のガスであり、25度以上、もしくは特定の成分が含まれていることです。天然温泉の定義は明確にはないものの、人工温泉の対比として使用され、いわゆる温泉法で定義された天然由来の温泉を指します。
日本温泉協会が制定した「天然温泉表示マーク」が掲示されている温泉は、天然温泉である証なので、温泉に入る際は、ぜひチェックしてみるとよいでしょう。
また、名湯として知られる山梨県・石和温泉にお越しの際は、石和温泉唯一の老舗旅館である「糸柳」にぜひお越しください。極上の天然温泉(アルカリ性単純温泉)をご用意して、お待ちしております。
Category
Archive
- 2025年(29)
- 2024年(42)
- 2023年(38)
- 2022年(36)
- 2021年(47)
- 2020年(21)